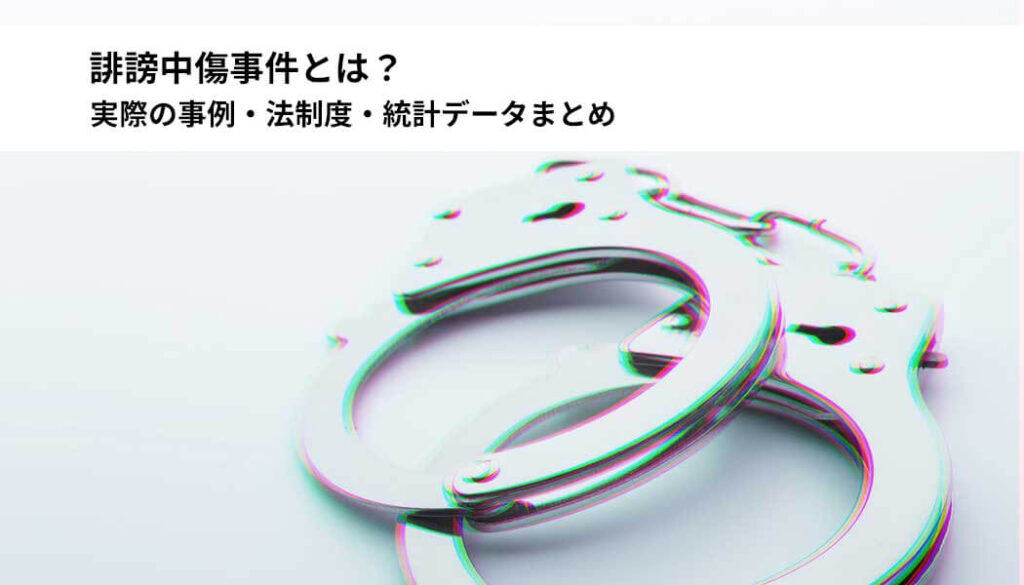
SNSや掲示板といった匿名性の高い環境では、誹謗中傷が発生しやすい傾向があります。
近年は、こうした書き込みが発端となるトラブルや事件が増加しており、社会的な関心も高まっています。
この記事では、実際に発生した誹謗中傷事件の具体例を紹介するとともに、発信者情報開示に関する統計、メディア別の炎上傾向、罪名別の刑事事件件数の推移など、公的なデータや独自調査データを交えて誹謗中傷問題の現状を多角的に整理しています。
あわせて、関係する法律についても解説します。
2022年7月7日、侮辱罪が厳罰化されました。
これは、インターネット上での誹謗中傷が社会問題として深刻化していることを受け、国の審議会などで検討が進められてきた結果です。
改正前は「30日未満の拘留、または1万円未満の科料」にとどまっていた刑罰が、改正刑法により「1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」となり、法的な抑止力が強化されました。
誹謗中傷対策を考えるうえで、侮辱罪の適用範囲や今後の運用動向は、重要な基準の一つとなる可能性があります。
ここからは実際に事件となった誹謗中傷事件について紹介します。
学生たちをとりまく「いじめ問題」は学校の中だけでなく、ネットにも広がっています。
2005年には茨城県で「学校裏サイト」による訴訟が起こされています。
高校入学後まもない女子学生が学校裏サイトで中傷され、多額余儀なくされたとして元同級生とその両親を相手取り、慰謝料を請求する民事訴訟を起こしました。
学校裏サイトでは女子学生の実名を挙げて「調子乗りすぎ」「消えろ」「いい子ぶってると殺すぞ」などと書き込んできます。
この結果、入学後間もない女学生には誰も近寄らず、ひとりで過ごすこととなりました。
書き込みの内容から殺される恐怖を植え付けられ警察に相談。書き込んだ元同級生に直談判したものの好転せず、2005年6月に退学を余儀なくされました。
その後元同級生とその両親を相手取り、2008年2月に200万円の慰謝料を求める民事訴訟を起こしました。
元同級生からは和解の提案がありましたが断ったと報じられています。
出典:マイナビニュース
2017年、滋賀県内の高校生を中傷する内容をSNSへ投稿していたとして東京都内の無職の少年が逮捕されました。
中傷された少年は「ごめん俺もう無理や」と書かれた遺書を残し自殺してしまいます。
SNSでの中傷行為は2015年7月~2016年9月に渡り続けられ「さまざまな女ユーザーに迷惑行為を行い、最終的にはそんなことをやっていないと逃げ惑っている」と投稿されていました。
高校生は警察に相談しましたが、自宅で首をつって自殺してしまいます。
その後、高校生の父親が被害届を提出しています。
容疑者の少年は容疑を認めているとのことです。
出典:J-CASTニュース
警視庁は、東京都千代田区に所在するゲーム会社の業務を妨害したとして、21歳の男子学生(東京都調布市在住)が書類送検されました。「殺しに行く」というメッセージを同社のホームページに送信した疑いです。
男子学生は昨年5月19日の夜11時半ごろ、同社の問い合わせフォームから「明日の午後3時にお前らくそ黄色人種を殺しに行きます」といったメッセージを送り、警察への通報や社員の避難などを要求することで業務を妨害した疑いがあります。メッセージには、「死ね」という言葉が約300回ほど書かれていたとのことです。
容疑者は同社のオンラインゲームのユーザーであり、調査に対して「負けが重なっていて、ゲームの設定がおかしいとイライラして書き込んだ」と話しているとされています。
出典:朝日新聞デジタル
岡医師は、明らかに人格攻撃だと弁護士から判断された40件あまりについて「発信者情報開示命令」を申し立てました。
その結果、20人以上の投稿者を特定し、投稿の削除や和解金の支払いといった示談や和解につなげました。
出典:NHKニュース
そのほかの事件例を一覧化して紹介します。
| 年度 | 概要 |
|---|---|
| 2005年 | 学校裏サイトによる誹謗中傷で女子学生が退学 |
| 2015年 | SNSなりすましによる誹謗中傷で訴訟 |
| 2016年 | 「寿司に異物が入っている」と虚偽の情報をSNSに投稿したとして無職男性を逮捕 |
| 2017年 | SNSによる誹謗中傷で高校生が自殺 知人男性を中傷するビラを貼った女性研修医が逮捕 |
| 2018年 | 政治家のSNSに誹謗中傷したとして訴訟 |
| 2020年 | 元アイドルを掲示板で中傷し2人が逮捕 |
| 2025年 6月 |
兵庫県議に対しSNSで名誉毀損する書き込みをしたとして男性が逮捕 |
| 2025年 7月 |
殺害事件の遺族に対し、SNSで50回以上虚偽の投稿を繰り返し、死者の名誉を毀損した疑いで書類送検 |
インターネット上の誹謗中傷は、X(旧Twitter)やInstagramといったSNSによって拡散・可視化されやすくなっています。
SNSの普及に伴い、これらのプラットフォームを通じて誹謗中傷に関連する事件が多発するようになりました。
SNS上での誹謗中傷は、現実世界に深刻な影響を及ぼすこともあります。
著名人や公共の人物がSNS上で攻撃を受け、精神的な苦痛や社会的信用の損失につながる事例も報告されています。
さらに、SNSの匿名性は加害者の責任を不明瞭にし、被害者が法的救済を受ける際の障壁となるケースも少なくありません。
中には、誹謗中傷が原因で被害者が自殺に追い込まれたり、集団リンチに発展したりする深刻な事例も確認されています。
こうした事件は、SNSという情報発信ツールの影響力の大きさと、誹謗中傷が個人に与えるリスクの深刻さを社会に改めて認識させる契機となっています。
このような状況を受け、SNSプラットフォーム各社は誹謗中傷対策を強化しています。
情報流通プラットフォーム対処法とは?企業が知っておくべきポイントと対策
利用規約やコミュニティガイドラインの改訂、誹謗中傷の報告機能の整備など、予防と是正の両面から対応が進められています。
加えて、機械学習や人工知能(AI)を活用し、誹謗中傷を自動で検知・削除するための技術開発も進行中です。
とはいえ、SNSと誹謗中傷の関係を根本から断つのは容易ではありません。
匿名性や情報の拡散性といったSNS特有の性質が、問題の構造を一層複雑にしています。
中でも、Xはその仕組み上、誹謗中傷が発生しやすい構造を持つプラットフォームといえます。
利用者数の多さに加え、設計上の匿名性や投稿形式が、誹謗中傷を助長する要因となっているためです。
Xではユーザーが匿名でアカウントを作成でき、プロフィール情報も限定的に設定できることから、投稿者の身元を特定しづらいという側面があります。
こうした匿名性が、攻撃的な言動のハードルを下げる一因となっています。
さらに、Xの投稿には文字数制限があるため、簡潔な情報伝達に適している一方で、感情的な表現や断定的な発言が強調されやすい傾向も見られます。
その結果、一部のユーザーが誹謗中傷的な言葉を選択する傾向があることも否定できません。
このような複数の要因が重なり、Xは誹謗中傷が発生しやすい環境の一つとなっているのが現状です。
匿名で書き込みが可能なインターネット上では、軽い気持ちで投稿した内容が誹謗中傷と見なされ、刑事事件に発展するリスクもあります。
たとえば、インターネット上であっても、公然と誹謗中傷を行えば、名誉毀損罪や侮辱罪に問われる可能性があります。
名誉毀損罪には、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が、侮辱罪には1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、あるいは拘留または科料が科される可能性があります。
両者の主な違いは、「事実の摘示(てきじ)」があるかどうかという点です。
たとえば、「不倫している」「犯罪者である」といった、具体的な事実を示す表現は、たとえ内容が真実であっても名誉毀損罪に該当する可能性があります。
一方で、「バカ」といった、事実の有無に関係なく評価だけで成り立つ表現は、侮辱罪の対象となると解釈されています。
また、名誉毀損罪と侮辱罪のいずれにも「公然に」という要件が含まれており、この点も重要です。
「誰でも閲覧・理解できる内容」のほか、特定の人物だけが理解できるあだ名や隠語を用いた表現であっても、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性があります。
名誉毀損罪に該当する誹謗中傷は、求める対応や目的に応じて、刑事事件にも民事事件にもなり得ます。
その違いは、加害者が負う責任が「刑事責任」か「民事責任」かという点にあります。
たとえば、損害賠償や謝罪広告などを求めて裁判所に提訴する場合は民事事件にあたります。
一方、警察が捜査に着手し、逮捕などの手続きが行われた場合には、刑事事件として扱われます。
いずれの場合も最終的な判断は裁判所によって下されますが、判断基準には違いがあります。
刑事事件では、提示された事実によって被害者の社会的評価が低下したかどうかが主な判断材料となります。
一方で、民事事件では、事実の提示に加え、被害者の名誉や精神的苦痛にどの程度の影響が及んだかも争点になります。
また、刑事事件では「故意」がなければ名誉毀損罪は成立しません。
これに対して、民事事件では過失であっても、不法行為として成立する可能性があります。
さらに、「公然性」も重要な要件の一つです。
刑事事件では、誹謗中傷が公然に行われたことが前提となります。
一方、民事事件では、原則として公然性がなくても名誉毀損の成立が認められる余地はありますが、社会的評価の低下が成立要件となるため、実務上は公然性がない場合に名誉毀損と認められるケースは少ないと考えられます。
参考
誹謗中傷になる言葉一覧!罪に問われる・訴えられる例文をリストで紹介|ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)
SNS上の誹謗中傷が増加傾向にある中で、名誉毀損罪の犯罪件数にも変化が見られます。
政府が公開する「検察統計年報」では、名誉毀損罪に関する受理件数が毎年集計されています。
この統計によると、集計が開始された平成18年(2006年)には677件だったのに対し、令和3年(2021年)には1,000件を超えており、年々増加傾向にあることがわかります。
一方で、同年の他の刑法犯の件数と比較すると、たとえば殺人事件が約1,500件、脅迫事件が約2,000件といった規模であるため、名誉毀損罪の件数は相対的には少ない部類に入ります。
誹謗中傷は身近で起こりやすい問題と思われがちですが、実際には刑事事件化する例はそれほど多くありません。
その背景には、名誉毀損による問題の多くが民事上の損害賠償請求として解決される傾向にある点が挙げられます。
被害者にとっても、「加害者を罰してほしい」という刑罰的な感情よりも、損失の補填や謝罪など、実質的な回復を求める意向が強いと考えられます。
そのため、刑事事件としての件数が少ないことは、問題の軽さではなく、対応手段の選択が民事中心になっている現状を反映しているといえるでしょう。
インターネット上で誹謗中傷の被害を受けた場合、冷静かつ適切な手段を講じることが重要です。 状況に応じて、以下のような対応が考えられます。
参考
誹謗中傷の相談ガイド|相談先の選び方や上手に相談するコツを解説|法律相談ナビ
誹謗中傷に対し、感情的な反論や個人での情報発信によって事態が悪化するケースも少なくありません。
たとえば、SNS上で反論したり、自身のブログで説明を加えたりした結果、さらなる批判が集まり、問題が拡大してしまうことがあります。
そのため、まずは第三者の専門機関や法律の専門家など、客観的かつ適切な知見を持つプロに相談することが望まれます。
誹謗中傷対策センターでは、誹謗中傷に関するお悩みや、投稿への対応方法についてのご相談も受け付けております。
インターネット上の書き込みに関してお困りごとがある場合は、お気軽にお問い合わせください。
