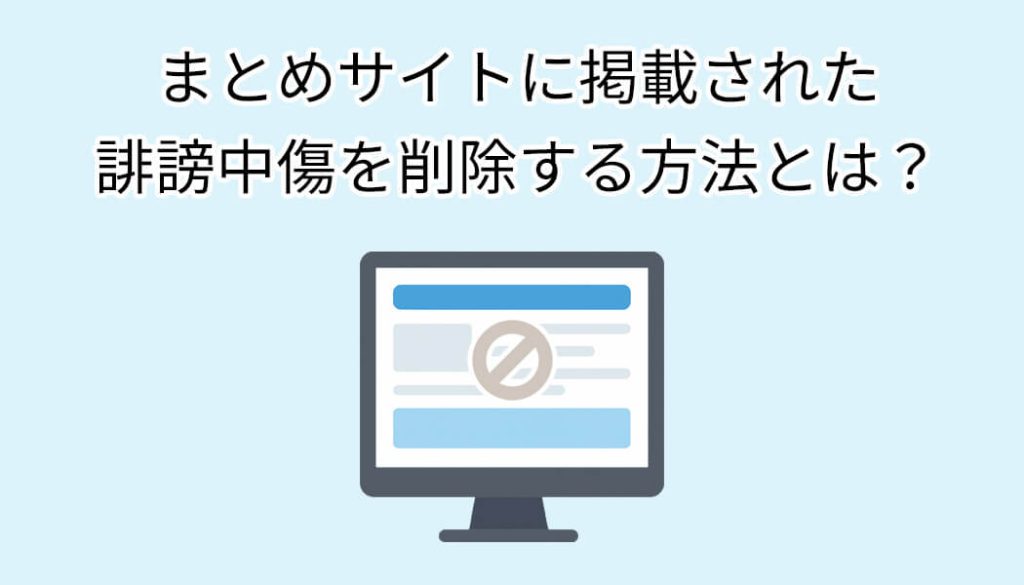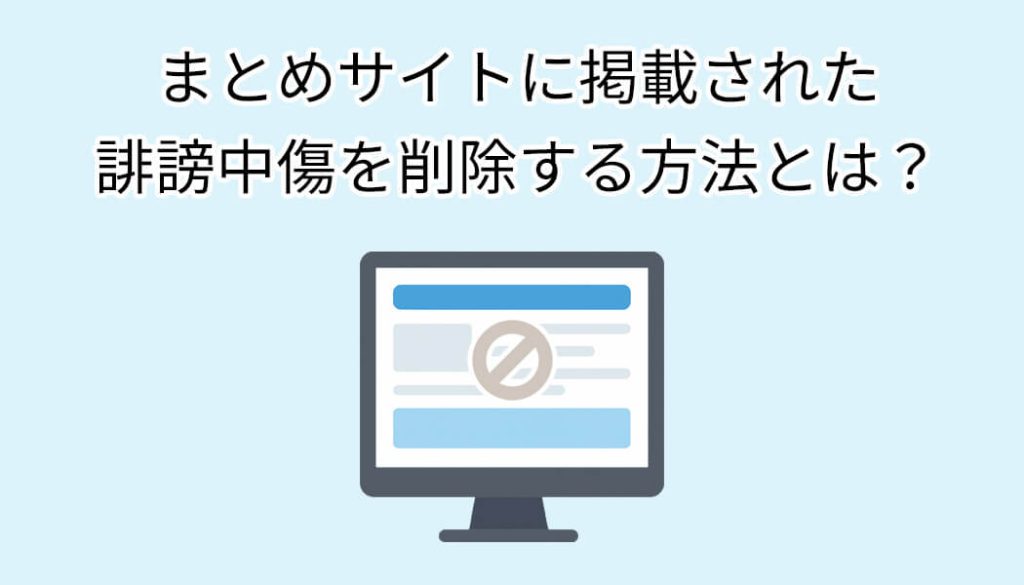
まとめサイトに掲載された誹謗中傷を削除する方法とは?
インターネット上には、匿名掲示板やSNSの投稿を収集し、再編集して公開する「まとめサイト(キュレーションサイト)」が数多く存在します。
ニュースの要約や趣味の情報共有など有益な面もある一方で、根拠のない噂や誹謗中傷が転載され、個人や企業に深刻なダメージを与えるケースも少なくありません。
一度ネット上に公開された情報は、検索エンジンを通じて誰でも閲覧できるため、信用や評判への影響が長期化するリスクがあります。
そこで本記事では、
- まとめサイトとはどのような仕組みのサイトなのか
- 誹謗中傷や虚偽情報が掲載された場合にどのような削除依頼ができるのか
について解説し、個人・企業が取れる具体的な対応策を整理します。
まとめサイトとは?
「まとめサイト」とは、インターネット上に点在する情報を収集・編集し、1つのページに整理して公開するウェブサイトのことを指します。
別名「キュレーションサイト」とも呼ばれ、匿名掲示板の投稿、SNSの発言、ニュース記事などから引用・転載し、それらを話題ごとにまとめるのが一般的な運営スタイルです。
本来は「多様な情報を手軽に確認できる」という利便性があり、ユーザーにとって役立つケースもあります。
しかし同時に、次のような特徴が問題視されやすいのも実情です。
- 匿名掲示板の発言を無断転載
- → 信憑性の低い情報や感情的な書き込みがそのまま拡散される。
- アクセス数や広告収益を優先
- → 誹謗中傷やスキャンダル的な内容ほど目を引くため、事実確認が甘いまま掲載される傾向がある。
- 運営者の所在が不明確
- → サイトに連絡先が記載されていないケースも多く、削除依頼が難航する原因となる
さらに、一度掲載された記事が長期間にわたり検索結果に残り、個人や法人の評判を大きく損なうリスクがあります。
まとめサイトでの誹謗中傷がもたらすリスク
まとめサイトに誹謗中傷や虚偽情報が掲載されると、個人・企業の両方に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
特に、記事が検索結果で上位に表示される場合、その影響は長期化しやすいのが特徴です。
個人の場合
- 就職・転職活動への影響
- → 採用担当者が名前を検索した際に誹謗中傷記事が目に入ると、印象が悪化する可能性があります。
- 人間関係への影響
- → 家族や友人、知人が閲覧することで、信頼関係や評価が損なわれることがあります。
- 心理的負担の増加
- → 誹謗中傷にさらされることでストレスや不安が増大し、日常生活に支障をきたす場合があります。
企業の場合
- 顧客離れ・売上への影響
- → ネガティブな口コミや虚偽情報が広まると、商品・サービスへの信頼低下につながります。
- 取引先やパートナー企業からの信用低下
- → 公開情報は社外関係者にも容易に閲覧されるため、契約・提携判断に悪影響を及ぼすことがあります。
- 採用・人材確保への影響
- → 求職者が会社情報を検索した際に不適切な記事が見つかると、応募者数や質に影響が出る可能性があります。
まとめサイトの情報は、一度ネット上に出ると完全に消えるのが難しく、検索結果を通じて長期的に目に触れるため、被害が長引くケースが少なくありません。
そのため、誹謗中傷情報を確認した時点で迅速に対策を検討しましょう。
削除依頼を検討すべきケース
まとめサイトに掲載された情報すべてを削除できるわけではありません。
しかし、以下のようなケースでは削除依頼を検討する価値があります。
- 1. 虚偽情報・事実と異なる内容が掲載されている場合
- 実際には起きていない出来事や、誤解を招く表現が書かれている場合
- 虚偽情報によって個人や企業の信用・評判が損なわれる可能性がある
- 2. 名誉毀損・プライバシー侵害に該当する場合
- 個人を特定できる情報(氏名・写真・住所など)が無断で掲載されている
- 社員や顧客の情報が公開され、業務上の秘密が漏洩している
- 誹謗中傷的表現や侮辱的な言動が含まれている
- 3. 無断転載や著作権侵害のケース
- 自社・自身が作成したコンテンツ(文章・画像・動画)が許可なく転載されている
- 著作権侵害に該当する場合は、法的根拠に基づいた削除依頼が可能
- 4. その他、早急な対応が望ましいケース
- 記事がSNSなどで拡散されており、さらに被害が広がる恐れがある
- 競合他社や第三者が意図的にネガティブ情報を拡散している可能性がある
これらのケースでは、感情的に反応する前に、冷静かつ根拠を整理して削除依頼の準備を進めましょう。
削除依頼の方法
まとめサイトに掲載された誹謗中傷や虚偽情報を削除するには、ケースに応じて適切な手段を選びましょう。
ここでは、個人向け・企業向けに分けて具体的な方法を解説します。
個人向けの削除依頼方法
- 1. サイト運営者への直接依頼
- サイト内の「お問い合わせフォーム」や「運営者情報」から連絡
- 記載内容:削除を求める理由(例:プライバシー侵害、名誉毀損など)
- ポイント:感情的にならず、冷静に具体的な根拠を示す
- 2. 検索エンジンへの削除申請
- Google検索などで個人情報保護やプライバシー侵害を理由に申請可能
- 申請が通ると、検索結果から該当ページのリンクが削除される
- 3. 広告配信業者・サーバー管理会社への連絡
- 運営者が不明な場合、広告ネットワークやサーバー提供会社に報告
- 規約違反や法令違反を理由に、掲載停止や削除の対応を促せる
- 4. 専門家・弁護士への相談
- 名誉毀損や著作権侵害の法的措置(発信者情報開示請求、削除請求訴訟など)
- 専門家を介することで、削除がスムーズになる
企業向けの削除依頼方法
- 1. 社内広報・法務を通じたサイト運営者への連絡
- 専門部署から正式な文書で削除依頼
- 法的根拠や事業への影響を明示することで、サイト運営者への説得力が高まる
- 2. 広告ネットワーク・サーバー管理会社への報告
- 会社名や商品名が誤って掲載され、信用に影響する場合
- 規約違反や商標権侵害などを理由に、早期対応を求められる
- 3. 逆SEO・検索結果対策
- ネガティブ記事が検索結果上位に表示される場合に有効
- 自社サイトやプレスリリースなど、信頼性の高い情報で上位表示を目指す
- より詳しい逆SEOの具体的手法や費用感については、下記で詳しく解説しています。
実践的な施策例を確認したい方はこちらも併せてご覧ください。
詳細記事
逆SEO対策とは?効果・費用・具体的な手法まで徹底解説
- 4. 弁護士・専門業者による法的対応
- 発信者情報開示請求や削除請求訴訟など、必要に応じた法的措置
- 企業の信用・ブランドを守るため、迅速な対応が重要
代表的な媒体と削除依頼窓口
まとめサイトは、独自に運営されるものも多いですが、ブログサービスを利用して公開されているケースも目立ちます。
代表的な媒体と削除依頼窓口の一例を以下にまとめます。
※横にスクロールできます。
削除依頼時の注意点
まとめサイトや検索結果から情報を削除する際には、以下のポイントを注意しましょう。
- 1. 削除が必ずしも認められるわけではない
- 運営者が自主的に削除するかどうかはケースによる
- 法的根拠がある場合でも、対応に時間がかかることがある
- 感情的に依頼すると対応が遅れる可能性があるため、冷静かつ具体的に理由を提示する
- 2. 早期対応が被害の拡大を防ぐ
- 記事が拡散すると、検索結果やSNSで長期間残る可能性がある
- 発見した時点で迅速に削除依頼や法的手段を検討することが重要
- 3. 個人情報や証拠の整理を行う
- 削除依頼には、掲載箇所・該当ページURL・掲載内容のスクリーンショットなどを整理して提示
- 法的措置を検討する場合は、証拠資料の確保が不可欠
- 4. 専門家や弁護士への相談
- 削除が難しい場合や、法的リスクが伴う場合は専門家に相談
- 専門家のサポートを受けることで、対応がスムーズかつ確実になる
まとめ
まとめサイトは、情報収集の手段として便利である一方で、誹謗中傷や虚偽の情報が掲載されやすいというリスクを抱えています。
個人であれば就職や人間関係に、企業であれば顧客や取引先からの信頼に深刻な影響を与えることがあり、その被害は長期にわたることも少なくありません。
もし不利益な情報を見つけた場合、まずは落ち着いて事実関係を整理し、削除依頼を検討しましょう。
サイト運営者への連絡や検索エンジンへの申請、法的措置など、対応の選択肢はいくつも存在します。
しかし、すべてのケースでスムーズに解決できるわけではなく、専門的な知識や経験が求められる場合もあります。
被害を放置すれば、信用の低下や心理的負担はさらに大きくなります。
だからこそ、早い段階で適切な対処を講じることが、自分や会社を守る最も確実な手段といえるでしょう。
誹謗中傷対策センターに相談
当誹謗中傷対策センターでは、まとめサイトや匿名掲示板に掲載された誹謗中傷・虚偽情報への対策サポート、逆SEO対策など、ネット上の風評被害に関するご相談を承っております。
「どの対応が適切かわからない」「自分だけで進めるのは不安」と感じる方は、ぜひご相談ください。
サイバーパトロールとは?警察から委託された民間の役割や種類を解説